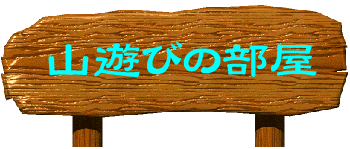
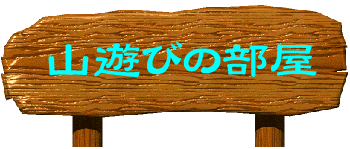
2000年9月号
10 月のハイキング予定
10月のハイキングは紅葉を楽しみたいと思います。少し遠出になりますが安達太良山に行くことにしました。。
ハイキングに参加されたい方は、【下山】まで連絡下さい。
また、是非自分の登りたいと思っている山や要望、御意見等もお寄せ下さい。今後皆さんの御希望に添うように計画を立てたいと思いますのでよろしくお願いします。
- 実施日:10月18日(水) 今回も平日と致しました。実施日は多少の変更可能ですので都合の悪い方はその旨連絡下さい。
- 場 所:紅葉の安達太良連峰。鉄山(1709)、安達太良山(1700)、船明神山
- コース:安達太良連峰の西側、沼尻温泉から登ります。変化のある展望のよいコースです。
コースの概要を以下に記載します。詳細を知りたい方は私のホームページの安達太良山-沼尻コースを御覧下さい。(http//:member.nifty.ne.jp/simon99/)
登山口からすぐに白糸の滝展望台があります。少し登った後、滝の上流の昔硫黄(湯の華)を採集した沢に下り、沢沿いを沼の平手前まで進みます。ここから胎内コースに入り、急坂を登り胎内岩を潜って鉄山避難小屋に登りつきます。沼の平を周回するように鉄山から馬の背を通って安達太良山方面に進み、船明神・石筵分岐に着きます。安達太良山はここから空身で往復となります。分岐に戻り、船明神山から障子岩の上を通って沼尻温泉に下ります。
正味歩行時間(標準コースタイム) 約5時間程度です。
登山コース
登山口-沼の平・胎内コース分岐-湯の華小屋-胎内コース分岐-胎内岩-鉄山避難小屋-鉄山-安達太良山-船明神・石筵分岐-船明神山-障子岩-登山口- 集合場所と時間:集合場所は里美村道の駅6時です。
登山口までのルート:R349から東館でR118にのり、棚倉から県道44号(棚倉矢吹線)に入り矢吹ICで東北道にのります。磐梯熱海ICでおり、母成グリーンラインで沼尻温泉まで行き、そこから登山口まで多少荒れた林道を入ります。- その他:昼食は各自準備下さい。地図等お持ちの方は持参下さい。
雨天の場合は中止します。中止の場合は前日の天気予報により判断し参加予定者に連絡します。また、装備に付いては出来れば下記を持参下さい。
装備等 雨具、防寒着、水筒、地図、ヘッドランプ、ストック、手袋、非常食、常備薬
携帯電話を当日持参します。 090-2569-7672 下山
トピックス 今回は9月に出掛けた栄蔵室山の山行報告と私の最近の山行記録(富士山、鳥取の大山、福井の荒島岳)を報告します。
<栄蔵室山・和尚山>
9月20日 北茨城市の栄蔵室山及び和尚山登山。
栄蔵室山 登山口9:10-山頂10:40/11:40-登山口12:33
和尚山 登山口13:05-山頂13:25/14:10-登山口14:25参加者は小林啓治さん御夫婦、川本さん御夫婦と下山夫婦の6名。天気は晴れ。
まず、集合場所の中郷SAでハプニング。川本さんの車がSAにないのに本人達はいるのだ。
何と入口を通過してしまい出口の路肩に駐車中とか。高速道路は逆走できませんからね。登山口にはルートと栄蔵室山の説明の書かれた立派な看板が立っていた。出発前にこの前で写真を撮る。川本さんがちゃんと三脚を持ってきていました。
この看板には栄蔵室山の標高882mは、筑波山より標高が高く茨城県内での最高峰であると書かれています。勿論、茨城県最高峰は八溝山であるが、これは県境にあるので「県内」では最高峰ということらしい。この辺りは高原状になっていてブナも生えているそうである。
この登山口の標高は約750mくらいありますので、標高差が130m位の登りであり登山としては大したことがない。最初登山道は沢沿いの湿った道。小林さんの奥さんが泥濘に片足を突っ込み、靴が泥んことなる。沢の丸木橋からもツルリ。あやふくセーフ。
小林さん曰く「今日の山行は、ゴルフで言えば最初にOB、その後チョロチョロ、こんなことで無事カップインできるかね~」
林道に出る手前の標識の後に
ツチアケビを見つけました。
林道の途中から栄蔵室山の山頂が
見えました。やがて栄蔵室林道の枝道に出てここから山頂下までは林道歩き。山頂へは林道から離れてマイクロ鉄塔の脇を通って暫くで一等三角点のある栄蔵室山山頂についた。残念ながら樹林に囲まれていて展望は全くない。説明看板には日光連山や晩秋から冬には富士山まで見えると書かれているのに、これは看板に偽りありだ。山ぶどうの実がいっぱい。口に含むと酸味がある。果実酒にすると美味しい酒が出来るのだが・・・。道端の萩はもうお終いでツリフネやオトコエシが咲いていた。
茨城県最高峰と書かれている栄蔵室山の山頂往路を戻り無事登山口に着いた。まだ時間が早いので、まず近くの亀谷地湿原に行き、木道を歩く。今は水芭蕉もお化けのように葉が大きくなっているだけでした。
この辺りにはめったに来ないからと、更にもう一山登ることにして和尚山の登山口へ移動。
道路沿いに登山口の標識がある所に駐車して雑木林の坂道を登る。やがて唐松の植林の中を進み、最後は急登となり山頂の広場につく。小さな石の祠と三角点がある。 ヤマボウシの木がありたくさんの赤い実をつけていた。少し採って口に含むと甘い。これも果実酒にすると美味しい。周りの木にも木の名前が吊るしてある。ブナ、エゴノキ、ウリハダカエデなどの名が見える。小林さんは、山頂の叢で仰向けになり暫しお昼寝の時間。キノコ探しもしたが食べられそうなキノコは見つからなかった。お昼寝も終わりのんびりと下山を開始。
帰りは塙町の方に出てR349を通って帰りました。
山頂の祠の前で記念写真。以下私の山行記録です。ヴァーチャル登山を楽しんで下さい。
<富士山> 標高3776m
8月19~20日 富士山登山。 前夜発、早朝登山(8合目宿泊)
【コース】8月19日 途中でいっぱい休みあり。時間は参考程度です。
河口湖・吉田口5合目6:20-6合目7:00/10-7合目花小屋8:38/45-8合目白雲荘
11:15/50-久須志神社13:36/46-郵便局14:20/40-剣ヶ峰三角点14:54/15:10-
下山道分岐15:33/40-8合目白雲荘16:17翌日20日 8合目白雲荘7:00-8合目江戸屋7:13/8:15-須走口新5合目10:50
【注】この山行は私の所属しているハイキングクラブの主催したものに参加しました。
水戸を前夜バスで出発、談合坂SAで時間調整した後、5時頃に登山口である吉田口5合目に着く。ここはもう標高2400mあり雲の上だ。見上げると晴天の空の中に富士山が聳えていた。下は雲海が広がっていた。
【写真は5合目から見上げる富士山】準備をして6時過ぎから歩き始める。まだ車が通れる程の広い道。やがて6合目。
ここから本格的な登山道となる。上を見上げると山頂方向まで小屋の連なり、登山道が延々と続いている。「あんな所まで登るのか~」とちょっとうんざり。
6合目手前から見上げる登山道。ジグザグの登り道が延々と続く。
7合目に向かう途中に熔岩の露出した岩場の歩きがある。
下山道を荷物運搬のブルドーザーが降っていた。雲海が綺麗だ。
8合目の今夜泊まる小屋(標高3200m)に着いたが,まだお昼前。そこで元気な人は天気のよい今日の内に山頂まで行ってよいということで私共も出掛けました。
さすがに3000mを越えると空気が薄くなり(平地の60%)ゆっくりしか歩けないし、すぐ休みたくなる。道端では酸素を吸いながら休んでいる人もいる。まだ頭が痛くならないので高山病は大丈夫のようだ。
9合目も過ぎて山頂の久須志神社の狛犬と鳥居にやっと辿りつく。もう一息でお鉢の周りに登りつけるぞと元気を出して登る。神社,売店などで賑わっていた。
登りついた神社、売店などのある一角。お鉢周りをしないでここまでの人も多い。
火口の周りを一周するお鉢周りは1時間以上かかる。最高点の剣ヶ峰に行くにはお鉢周りをしなければならない。途中に富士山郵便局があり、登山証明書の葉書を買って自宅へ郵送する。富士山測候所のある剣ヶ峰の最後の登りはしんどい。
山頂の一角に2等三角点と日本最高峰富士山剣ヶ峰の石碑があり、ここで記念写真を撮る。やはり日本最高点に登ったと言う感動はそれなりにある。周りの眺めは最高。
剣ヶ峰から眺める富士山の火口。丁度火口の向こう側が登りついた所。
お鉢周りの途中から富士山測候所と剣ヶ峰
お鉢周りの途中から見た美しい雲の峰
翌日も晴天でした。私はこの日は山頂へは行かず、8合目の小屋から御来光を見ました。私は19日に富士山に登ったので、翌日夜中から出発して山頂で御来光を見るグループには加わらず、8合目の小屋から御来光を眺めました。
下りは須走り口へ下りました。夜中に山頂へと出掛けたグループと8合目の下り口で落ち合い、静岡県側へと下ります。
【写真は8合目の下り口から山頂方向の眺め】砂走りは足がずるずると潜るような砂礫の道で、登るには大変な下り専用の下山路である。文字通り走るように下ることも可能でしょう。
やっぱり下りは大変楽でした。富士山は一度は登ってみようとやってくる人が多く、夏場は観光地のような賑わいです。
砂走りを降って須走り口に下山の途中。オヤマソバやオンタデ等がきれいです。「富士山は眺める山で、登る山ではない」なんて言っていたのですが、登ってみると日本最高点を歩いていると言うことも加わりそれなりの感動が味わえ、「1度は登ってみる山だ」と思っています。
<鳥取の大山> 標高1711m
8月31日 大山登山 所要時間 約6時間30分(休憩時間含む)
【コース】夏道登山口5:55-1合目6:15-2合目6:30/38-3合目6:48-4合目6:58
-5合目7:09/20-6合目7:33-7合目7:45/50-山頂8:25/9:50-
岩室経由-6合目10:24/37-元谷分岐10:45/50-大神山神社奥宮11:30
-登山口駐車場12:30
関西(兵庫、和歌山)に帰省したついでに鳥取まで足を延ばして大山に登ってきました。意外と近く登山口まで3時間半ほどでした。前日午後に出発し、登山口駐車場で車中泊し、早朝に起きて登りました。 写真は前日高速道から降りたところから撮った大山の写真ですが、この日は山頂部に雲が掛かっていました。こちらから見ると「伯耆富士」「出雲富士」と言う名の如く富士山の形に似ていますが、少し方向を違えると別の山のように形が変わります。
この山も信仰の山で山麓のあちこちに古い神社があります。登りは夏道登山道を登りました。途中は美しいフナの林で日差しを遮ってくれます。合目表示があり、6合目辺りから低木帯となって展望が開けてきます。大山の崩落の激しい北壁などが良く見えます。
8合目を過ぎるとやがて特別天然記念物のダイセンキャラボクの純林の中の木道を歩くようになり、頂上も真近になります。(写真参照)
下には日本海や話題になった中海なども見えます。この日は南、東方向は雲海が広がっていてとてもきれいでした。
大山(弥山)頂上から剣ヶ峰への縦走路を見る。今は崩落が激しくなって通行止めとなっており、縦走は出来ませんが、写真左のピーク(弥山の三角点あり)までは行きました。
登りついた山頂からは大展望が広がり、とても気持良く1時間以上山頂で楽しんでいました。 右の写真は逆光でよく見えませんが、看板は「縦走危険」と書かれておりロープが張ってあります。更に通行禁止の看板があります。
しかし、その先の三角点のあるピークまでは山頂小屋のおじさんの案内でこっそりと行ってきました。
下の写真は南側の雲海、この展望板には四国の石鎚山や剣山まで載っていましたが、勿論見えません。右下の写真は西側の米子市方面ですぐ下に山頂の避難小屋が見えます。左端に見えるのが話題となった中海です。
弥山山頂の三角点(1711m)にタッチして御機嫌の瞬間です。 下りは5合目手前から分岐している行者コースに入り元谷へ下りました。
こちらからは崩落の激しい北壁が正面から見えます。
更に下って大神山神社や大山寺を観光して登山口に戻りました。入浴してさっぱりした後境港の魚市場に寄って鮮魚を仕入れてから帰途につきました。今回は大展望に恵まれ楽しい山旅でした。
6合目付近から見る崩落の激しい北壁
元谷は崩落した岩礫が流れてくるので大掛かりな砂防工事がされていました。大神山神社奥宮はなかなか立派な神社であった。すぐ横に下山神社と言うのがある。私の苗字と同じ名前で何だか変な感じ。
下山後米子方面に行く途中からの大山<荒島岳> 標高1523m
9月6日 荒島岳登山 歩行時間 約5時間半(休憩時間含む)
勝原登山口駐車場11:16-リフト終点11:56/12:10-尾根上休憩13:13/25-シャクナゲ平13:41-荒島岳山頂14:40/15:15-シャクナゲ平15:49/16:00-登山口駐車場16:40
荒島岳は日本百名山の一つで福井県大野市にあり、こちらも「大野富士」と呼ばれています。関西へ帰省からの帰り道に寄り道をして登りました。
帰省先を出たのは朝の5時でしたが、登山口に着いたのは11頃となっていました。この山は下から眺める山の姿がとてもよいのですが、急いでいたので途中で写真を撮るのを忘れてしまいました。従って山頂での写真しかありません。
登山道は最初スキーのゲレンデの急斜面を登るもので、日差しを遮るものが無くカンカン照りの中暑くて参りました。もう下ってくる人に出会いました。
リフトの終点からは美しいブナの森の中に入りホッとしました。大きなブナやミズナラの木が生えた原生林で秋には紅葉がさぞ綺麗だろうと想像されました。
シャクナゲ平から主稜線になり、約1時間の登りで山頂に着いた。
今日はもう時間も遅いので山頂には誰もいなくなっていました。
目の前に白山が見えますが、遠くの山は今日は霞んで見えません。大野盆地が稲で黄色く色付いていました。
山頂には三角点の他に荒島大権現の奥宮が祭ってあります。
実はこの他に無線中継所のコンクリートの建物や反射板等の人工構築物があって気分を壊されます。下りは往路をそのまま戻り、登山口に着いたのはもう5時近い時間でした。
山としては比較的地味な感じの山でしたが、ブナの森は美しかった。
登山道で見た山の花々
今回はもう花の時期が過ぎて秋の花に移ってきていましたが、それでも幾つかの高山植物に出合えました。晩夏に咲く高山植物と言うことで紹介します。
トモエシオガマ(富士山)
トモエシオガマ(荒島岳)
オトコヨモギ(富士山)
オヤマソバ(富士山)
ムラサキモメンズル(富士山)
ヤハズヒゴタイ(富士山)
コゴメクサ(大山)
オヤマリンドウ(荒島岳)
サラシナショウマ(大山)
サラシナショウマ(大山)
トリカブト(荒島岳)
不明です(荒島岳)御覧頂き有難うございます。ご感想、要望、登りたい山等あれば【下山】まで連絡下さい。
連絡先 下山和彦 E-mail::BZB11032@nifty.ne.jp ℡・FAX029-274-1872